ひげよ、さらば - 上野 瞭
『ひげよ、さらば』 - 上野 瞭
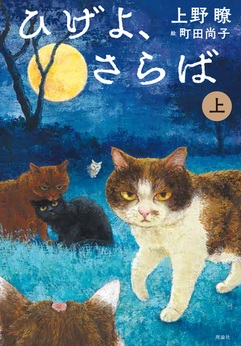
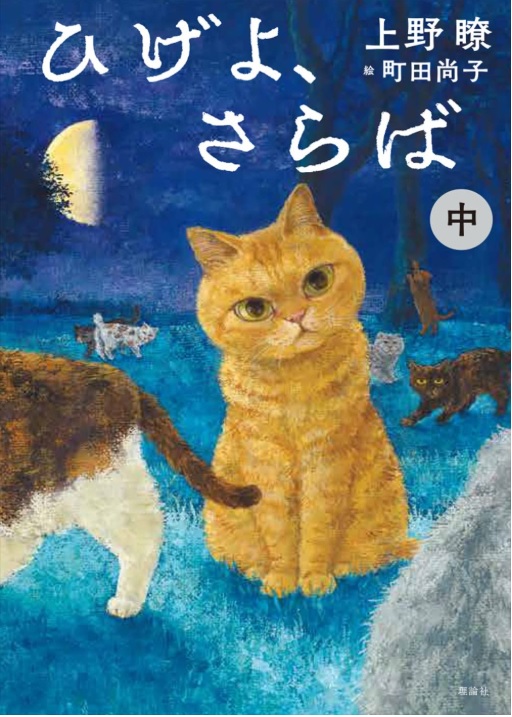
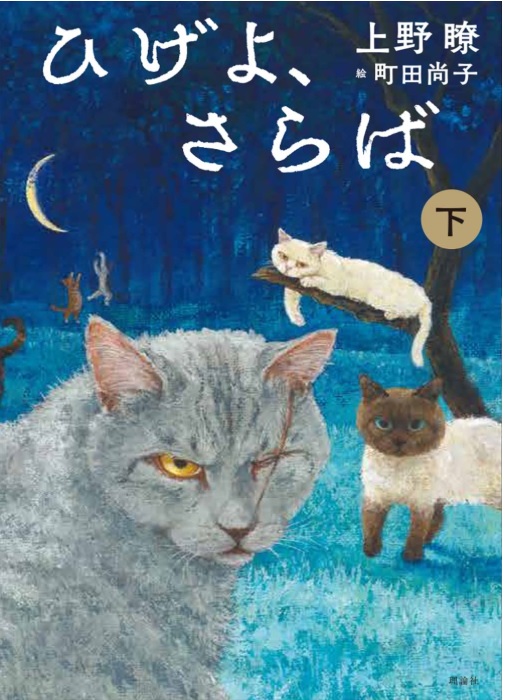
80年代に雑誌の読書評を読み、ぜひ買おうと思っていながら購入の機会が無かった作品を、ようやく購入して読んでみた。
絶版になっていたが、Amazonのマーケットプレイス(中古通販)で結構安価で購入できた。
そもそも作品を読んでいないのに20年も経って覚えているのは、書評自体が非常に良くできていたことと、その単なる書評中の『あらすじ』を読んで僕自身が頭の中にまったく別の物語を構築してしまった為だろう。
曰く、僕が頭ののなかに勝手に作り上げたストーリーは以下のようなものだった。
ある街で猫たちの抗争が起こる。二つのグループはそれぞれお互いを攻撃し双方にそれなりの被害がでる。そんな状況を憂いた参謀的な資質を持つ猫が、別の少しぼーっとしていて抜けているところがあるが人当たりの良い猫をリーダーに仕立て二つのグループを統合しようと画策する。短期間ではあるが抜けている(リーダーの資質がない)猫をリーダーとした『猫王国』は成立する。しかし権謀策術によって成立した『王国』にはやはり無理がありクーデターのようなものでリーダー猫は殺されてしまい王国は無に帰すこととなる。自分の策略のために犠牲となったリーダー猫への責任と自分の行為への清算のために参謀猫は自らの命を炎の中に投じる。
実際に読み終えてみるとまったく違う話だったことが理解できた。
まず抗争は『犬』対『猫』のものだったので、この部分を大きく誤解していた。書評がすべてのストーリーを書いてしまうのはある意味『ルール違反』なので、この程度の見込み違いはあって当然だが、『期待通り』とか『期待はずれ』とか云う判断は購入前のこういった『思い込みと実作品の誤差』にあるのだと言うことを強く実感した作品だった。
以下に(読後の)僕なりの書評を書いて見たいと思う。
僕が購入した作品は文庫版で上、下2冊に分かれているものだが、上巻と下巻との作品のバックに流れるトーンがまったく違うことにまず驚かされた。
上巻は記憶喪失の猫『ヨゴロウザ』が仲間を見つけ距離感を保ちながらもコミュニティに溶け込んでゆき、本来自由奔放な猫たちを『ひとつにまとめる』と言う目的意識を主人公たちが持っている為、(記憶喪失の猫という伏線を孕みつつ)前向きな部分が強いトーンで作品は進んでゆく。主人公の『失われた記憶を取り戻したい』と言う希望もあるし、失われていた部分が読者には提示されないので期待感もある。
しかし下巻に突入したとたん、ヨゴロウザの人格までもが一変してしまうように思えた。基本的には70年代の不良映画やその手のステレオタイプな物語で描かれたような『疎外感から拗ねて不良になりました』的な(現代の根本的な絶望感/閉塞感とくらべると)比較的甘ったれた不良化がヨゴロウザを襲う。その暗くネガティブな雰囲気のままストーリは展開するが、単なるリーダー猫の思春期の甘えた不良化とは違う様々なサブ・キャラクターたちの閉塞感とスペクタクルな死が綴れ織りように展開してゆく。そして最後は救いの無い絶望的なエンディングが(記憶の回復とともに)待っている。
作者が最終的に何を言いたかったのか解らないが、恐らく書き出しの部分で想定していたのはこの作品の後半部分ではないような気がした。また、この作品が児童文学として出版されたのは何かの間違いだし児童文学的なトーンはまったくと言ってよいほど作品中に見られない。後にNHKによって人形劇として放映されたらしいが原作と人形劇(見ていないがネット上にある感想では動物たちが生き生きと描かれたが明るい話だったらしい)はまったく別のものだと考えてよいだろう。
しかし、この作品が妙に心に残るものであるのは間違いない。恐らく80年代の出版された直後に読んでいたとしたら個人的に『人格形成に影響を与えた作品』になっていたと思われる。
たまたま想像(書評のあらすじから想像した物語)と現実(実際の作品)との間に20年以上もの歳月が横たわってしまった。こう言ったことってほとんどないはずなので僕にとっては貴重な体験をさせてもらった作品となった。
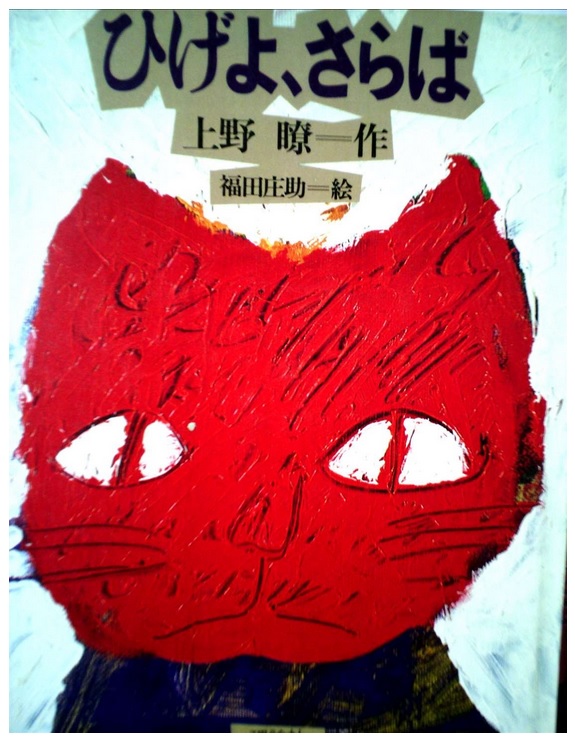
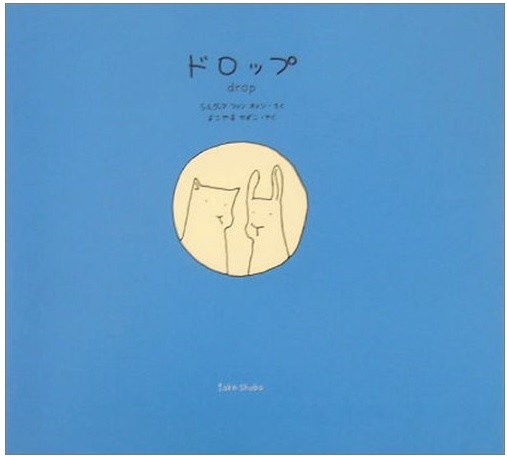
コメントを送信